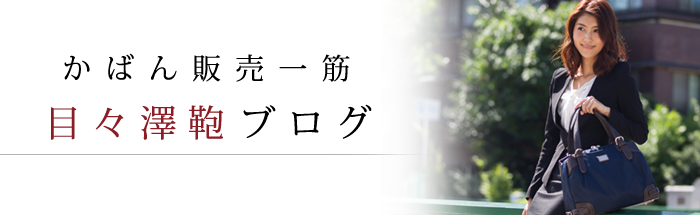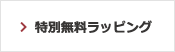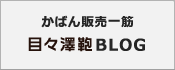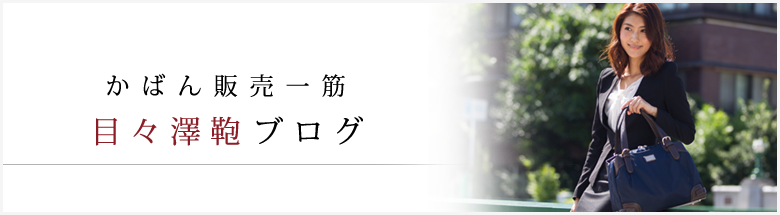
象革(エレファントレザー)の財布を使って幸せを呼び込もう
2021.02.05
2021年春、お財布の新調を検討されている方が多いのではないでしょうか?
立春を迎えた日からひな祭りの3月3日までに購入した財布を“春財布”と呼び、この時期に財布を買い替えると縁起が良いと昔から言われているのです。
そこで今回は、幸運をもたらすとされている“エレファントレザー”の財布をご紹介させていただきます。
“エレファントレザー”と聞いてワシントン条約を思い浮かべた方、詳しくは象革やワニ革の財布小物って販売して大丈夫?をご覧ください。
エレファントレザーの特徴
・摩擦に強く耐久性に優れている
・型押しでは表現できない本革ならではの毛穴やシワ、擦れなどが見られ、一つとして同じものがない
・草原を駆け回るワイルドなイメージと違い、起毛が柔らかくしっとりとしていて手触りがいい
・マットな質感なので落ち着いた雰囲気がある
・比較的手入れが簡単
・使いうほどに味わい深い表情に変化する“経年変化”を楽しめる
・希少価値が高いため高級である
なぜ象革は開運・幸運と呼ばれるのか
象は古くから世界的に幸運の神様や幸せの象徴とされてきました。
例えば、タイでは勇気と誇りの象徴とされています。かつて他国との戦争時、王は象に乗って戦いに挑んだそうです。そのため、象は“王を守り先陣を切って戦う”というイメージからそう呼ばれるようになりました。
インドではヒンドゥー教の神様、ガネーシャとして奉られています。障害を取り払い財産をもたらすとして事業開始と商業の神・学問の神とされています。
西洋では幸せの証とされ、古来よりヨーロッパの王侯貴族の気高さの象徴ともされ、持つ者を幸福へと導くと言われていました。 また、エレファントレザーの財布は風水的にみると、心の安定や後ろ盾の獲得、子孫繁栄などがあるようです。
幸せとの結びつきの深さを感じますね。象が世界的に愛される理由が分かります。
“春財布”のうちにお買い替えを検討されている方、象革財布を選んでみてはいかがでしょうか?
歴史にかかわった運命のカバン
2016.08.05
「アドルフ・ヒトラー」といえば史上最も名高い独裁者として知られています。彼が何度かの暗殺未遂事件に遭遇している中で、最も危機的だった1944年に立案された暗殺・クーデター計画があります。
ドイツを破滅から救おうと参加した軍の上級将校たちは、大本営である「ヴォルフスシャンツェ」に爆弾を仕掛けることを計画しました。1944年7月20日の午後、爆弾入り鞄をヒトラーの足元に置くことに成功し、数分後に予通り炸裂しました。しかし、ヒトラーは軽症に留まり、クーデター計画も頓座してしまうことに…。ヒトラーの直近にいたブラントがテーブルの脇に鞄を置きなおしたことで、威力が半減したのです。
その後の歴史は、私達が知っている通りのものですが、1945年5月、それに伴う降伏が早まっていたら歴史が大きく異なっていたでしょう。あの日置かれた鞄は、大きく歴史を変えていたかもしれない「運命のカバン」なのです。
歴史をたどってみれば、「運命のかばん」や「企みのカバン」が見つかるかもしれませんね。そんなワクワク感あります。
ランドセルの起源は軍の装備品
2016.06.30
「ランドセル」の語源はオランダ語
明治18年、東京に設立された学習院では、軍人が使用する「背嚢(はいのう)」に学用品や弁当などを入れ通学鞄として使用していました。この背嚢は、幕末に西洋式の軍隊制度が導入された際に取り入れられたもので、ランドセルのルーツといえるでしょう。
「ランドセル」という名前はオランダ語で背嚢を意味する「ransel(ランセル)」に由来するといわれ、現在まで受け継がれています。
伊藤博文の特注品
当時のランドセルは布のリュックサックのようなカタチだったそうです。現在のようなランドセルが誕生したのは明治20年頃のことであり、当時の総理大臣であった伊藤博文が、大正天皇の学習院入学を祝し、革製の丈夫な鞄を特注して献上したのが始まりとされています。
日本のランドセルは珍しい?
ランドセルはその後、背負うと両手が自由になるなどの長所から、小学生の通学鞄として広く普及しました。特に昭和30年代以降は全国の小学校に普及し、日本の小学生の必需品となっていきました。
実は、ランドセルのような通学鞄が普及している国は、ヨーロッパの一部を除いてほとんどありません。また通学鞄としてだけではなく、近年、海外では大人も使える実用性の高いファッションアイテムとして、ランドセルが人気を集めています。ランドセルは今や、日本独自に進化したオリジナル商品といっても過言ではないかもしれません。
「鞄」の語源と歴史
2016.05.23
「鞄」と漢和辞典を引くと「革をなめす職人」の意味があり、現代の日本で使われている意味が元来の中国語にはなかったようです。「鞄」は漢字で革職人を指す語であり、多くの国語辞典で「カバン」の語源は中国語で「ふみばさみ」を意味する「夾板(キャバン)」とされています。
しかし、明治期に生まれた「鞄」は革で包むの意から先に「鞄」の字があることを知らずにそのころ普及していた「カバン」という言葉の音をあてて作られた国字なのです。よって「鞄」は起源的に漢字とするのが正しいのですが、それを「カバン」と読むのは日本独自ということになります。
日本においてカバンを「ふみばさみ」と言っていた時代は、高貴な身分の人へ文を届ける際に無礼の無いように差し上げるための道具を指していました。この「ふみばさみ」は私たちが想像する手提げの「カバン」とは大きく違い、僧侶が担いで歩くものでした。
そもそも日本には手提げの携帯用具という物は少なかったようですが、平安末~鎌倉時代の初期に描かれた絵巻ものには曲げわっぱのようなものにひもをかけて担いでいる姿が描かれています。
また、江戸時代に描かれた風俗画では「風呂敷」が現在の「カバン」に最も近い用いられ方をしています。そんな中で、箱状の形ではありますが、天辺に取っ手をつけて「カバン」のように用いられた例があり、江戸で都市生活を営む人々の間で馴染みのある道具でした。
このようにして私達の使う「鞄」は変化をとげ、現在のような形になりました。
明治時代を代表する小物
2016.02.28
名刺入れやがま口の登場
小物とは財布、定期入れ、名刺入れなどの総称です。明治時代の小物、袋物の多くは煙管(きせる)で吸う「刻みたばこ入れ」だったそうです。価格は4円~40円(現在の2万円~20万円程度)で、高級なものもあったようです。また当時は、葉巻の舶来に伴う葉巻入れや、口金の輸入によるがま口、名刺入れなどの商品も新たに登場しました。
明治時代以降、煙管から巻きたばこが主流となるにつれ、刻みたばこ入れは巻きたばこ入れに姿を変えていきます。やがて現在のようなパッケージに入った巻きたばこが販売されるようになり、たばこ入れの需要は激減しました。
目々澤鞄の会社概要でもご案内の通り、カバン店として店を構える前身はこの喫煙具を販売していました。禁煙化が進む現在、メーカーのタバコケースの生産が減っている中、まだ必要とされている方々のために、オリジナル商品をはじめシガレットケースを積極的に販売しております。また、健康志向、健康ブームにのり需要が爆発的にふえているiqos を収納するアイコスケースもオリジナルブランドから発売しております。
藩札と長財布
紙幣が流通するようになった江戸時代には、各藩が独自に発行した藩札という紙幣が使用されるようになり、その藩札を入れるために財布、特に長財布が広まったといわれています。
明治時代以降は紙幣が発行されるたびに長財布の需要は増加していったようです。また、口金の改良に伴い、がま口も人気が高まっていったといわれています。
二つ折り財布の登場
第二次世界大戦後クレジットカードが使われ始めると、カードポケットのある二つ折りの財布が登場しました。その後、コンパクトで持ち運びやすい二つ折り財布は、クレジットカードが普及するにつれて急速に広まっていきました。
手提げカバンの誕生は紀元前9世紀!?
2015.08.25
手提げカバンのルーツ
手提げカバン(ハンドバッグ)の歴史は紀元前9世紀頃まで遡ります。その頃に現在のイラク北部であったメソポタミア地方で、古代アッシリア帝国の有翼神像が現代のハンドバックの大変にているようなものを持っていたことが始まりだといわれています。
ポシェットの登場
時代は流れ、中世ヨーロッパでは、現代のポシェットによく似たショルダーバッグのような形のバッグが登場しました。「pochette(ポシェット)」とはフランス語でポケットを意味します。ポケットには入りきらないものをスマートに持ち運びたかったということでしょうか。当時のポシェットは「オモニエール」と呼ばれ、付属のひもで腰のベルトに吊るして使用していたそうです。

「おふくろ」の由来とは?
一方、日本では、鎌倉~室町時代にかけて、女性が家の財産を管理するのが一般的でした。貴重品や金銭を袋に入れて管理していたことから、一家の中心となる女性を「お袋様」と呼んだそうで、それが「おふくろ」の語源する説があります。
明治時代になると、洋服の普及とともに手提げタイプの袋が外国から持ち込まれるようになりました。そして明治時代後期になって登場したものが、日本のハンドバッグのプロトタイプともいえる「オペラバッグ(今はあまりこの呼び名は使いませんが)」です。このオペラバッグはその名のとおり観劇用の布製バッグで、当時は「西洋風手提げ袋」と呼ばれていました。現代のような手提げバッグ(ハンドバッグ)が一般的になったのは、大正末期~昭和初期にかけてのことです。
明治維新と一緒に生まれた日本のカバン
2015.03.20
現在の鞄のプロトタイプ “物を入れて運ぶもの=鞄” と定めると、その歴史は人類史と同じくらい長くなってしまいます。江戸時代までの日本で、鞄の役割を果たしていたものとしては、医者が薬の持ち運びに使っていた薬籠(やくろう)、武将の鎧や兜を入れた鎧櫃(よろいびつ)、旅行の荷物入れに用いられた行李(こうり)などが挙げられます。 現在の鞄の原型となるものは18世紀のヨーロッパで誕生したといわれています。その後、鞄の製作は徐々に盛んになり、19世紀半ばには王室や貴族お抱えの鞄職人たちが次々と独立をしたそうです。
日本での最初の鞄
19世紀半ばは、日本では幕末~明治維新にあたります。文明開化によと外国の文化が一斉に入ってきた時期で、西洋の鞄もそのひとつでした。 日本初の鞄については諸説あり、一説では、大阪の商人がフランスから持ち帰った鞄を参考にして作ったものだとされています。また、ある馬具職人が外国人から鞄の修理を依頼され、後にそれを真似て作ったのが最初、という説もあります。
日本のカバンの原型ともいわれる 柳行李を写真でご紹介します。

かばんの街・兵庫県豊岡市 エンドー鞄所蔵
「カバン」の故郷はオランダ?
鞄の製作は次第に本格化し、明治20年頃には日本にも鞄の専門店が登場しました。鞄の種類も、手提げ丸型鞄や学生鞄、抱鞄など、用途やデザインによってどんどん細分化されていきました。 また、オランダ語のkabas(カバス)が語源とされる「カバン」という名前も、「鞄」という文字も、明治時代中期頃から一般化したといわれています。ただ、カバンの語源に関しては中国語に由来するという説などさまざまあります。
「カバン」の歴史をもっと知りたいなら資料館へ
袋物参考館に行ってみよう! 世界各国でカバンに何を入れて人は使ってきたのか。 目々澤鞄も現在も取引のある プリンセストラヤ内にそれはあります。 また東京都内に エース世界のカバン館もあります。
鞄のルーツ 柳行李(やなぎごおり)
2012.02.09